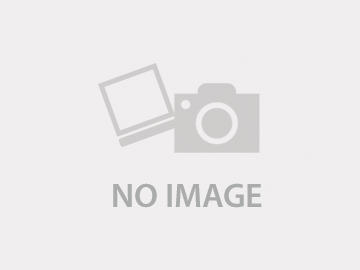決して信じてはいけない信用創造 すき家とゴールドマンサックスとリーマンショック
先に何をされるかわからないものを信じて、投資とかしてはいけない。
なに書いているか、なんとなくしかわからないけど、
信用できるかどうかわからない人や物をキチンと判別せずに
人生やお金を投資するのは、ボンクラがすることだとか。
それをカモにしてお金儲けしている詐欺で
この世のは成り立っているとか。
やっぱりというか、借金漬けにして、働かないといけないという感じにして
世の中の人は働くというシステムになっている。
金持ちとか、そういう人達は優遇されるようにできるシステムとか。
新しい妻がどうだとかって書いてるみたいだし。
馬鹿馬鹿しいですね。
すき家にいって食べている低所得、中所得者は、
こんな感じのシステムで生きているんだなと。
余計に行く気がしなくなってきた。
知らずに働いて死んでいくのが
低所得者たちの本当の
幸せなのかもしれない。
愛がどうだのこうだの話していって、
そういう人達とは戦わずに
生きていくというか・・・。
アメリカがかわったとは思うから、
それでどうなるかもあるでしょうけど。
おそらく、今の日本の感じの状態って、
ゴールドマンサックスとかそういう人達って
ディープステートってなるのかもしれないけど、
まだ、その組織で日本の政府、官僚とか成り立っているように見えるし。
どうなるかとか、どうするかなのか・・・、
日本の場合、どうなるかって事な気がするけど。
『世紀の空売り(The Big Short)』―“リーマン・ショックの本質”
金融機関に勤務。海外が長く(通算18年)、いつも日本を外から眺めていたように思う。帰国して、社会を構成する一人の人間としての視点を意識しつつ読書会を続けている。現在PCオーディオに凝っている。
◆強きを助け、弱きをくじく
銀行で働いていた頃の話である。若気の至りで正義感を振りかざした発言をしたところ、ある役員から「銀行員というものは、強きを助け、弱きをくじくものだ」と諭されたことがある。その時は反発を感じたが、時を経るに従ってその言葉の中にある真理を、諦観を伴って受け入れられるようになった。
現在では、これは日本だけではなく、世界共通の真理だということも知っている。そうした私が、今さら米国の投資銀行のモラルハザード(倫理観の欠如)に驚くことはおかしいのだが、リーマン・ショックを背景にしたノンフィクション『世紀の空売り』に描かれた米国のエリート金融マンたちの倫理観の崩壊には衝撃を受けた。
金融界で長年働いてきた身でありながら、本書を読むまで、リーマン・ショックを、住宅バブルの崩壊を契機とした「金融危機」の一つと捉えていた。本書を読むことで、もっと深刻で根深い倫理観の崩壊が背景にあったことに気づかされた。これが今回、本書をとりあげる理由であり、問題の根本に何があるか考えてみたいと思う。
◆本書について
『世紀の空売り(”The Big Short”)』は、米国の作家マイケル・ルイス(*注1)によって2010年に書かれたもので、米ニューヨークのウォール街を舞台に、サブプライム住宅ローン債券市場の破綻(はたん)に賭けた男たちを描いている。
2015年に映画化され、アカデミー賞脚色賞を獲得している(*注2)。日本では『マネー・ショート 華麗なる大逆転』の題名で16年に公開された。映画を見たが、難解な金融取引を、コメディータッチで分かりやすく描きつつ、原作の持つ批判性を失わない良作に仕上がっていた。
◆本書のストーリー
米国の大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したのは、08年9月15日であるが、前年の07年には「サブプライムローン危機」が顕在化しており、それがリーマン・ショックを生み出し、世界的な金融危機につながっていった。
その少し前に、本書の主人公であるファンドマネジャーたちは、別々の方法でサブプライム住宅ローン債券市場の異変に気がついて、市場崩壊にファンドの全資金を賭けるのである。ニューヨークのヘッジファンドを率いるアイズマン、カリフォルニアの隻眼(せきがん)のファンドマネジャーのバーリ、若き個人投資家マイとレドリーである。
彼らは、サブプライム住宅ローン債券市場が、投資銀行の金融工学を駆使した錬金術に操られ、金儲けに利用されていることに気がつく。市場の狂乱を目の当たりにし、金融システムの欺瞞(ぎまん)性への義憤が彼らを動かす。市場の下落に賭ける(空売りをする)のである。やがて市場は崩壊し、彼らの正しさが証明され、大金を手にするが、勝利感よりも一種の虚しさにとらわれる。
◆サブプライム住宅ローン債券市場について
リーマン・ショックが何であったかということを知るためには、「サブプライム住宅ローン」「証券化」「CDO」「CDS」といった金融用語の理解が必要だ。映画のようにいかないが、できるだけ分かりやすくしたつもりなので、少し我慢してお読み頂きたい。
サブプライム住宅ローン
優良(プライム)層より下位の、低所得あるいは信用力が低い層向けの住宅ローンを指す。始まりは、ホーム・エクイティ・ローン(*注3)だとされる。当初は、低所得層へ相対的に低利な金融手段を提供する目的があったが、投資銀行が参入して債券化のために粗製乱造され、商品としての質が低下していく。
サブプライム住宅ローンの証券化
証券化は住宅ローンを集めて、小口の債券に変えること。RMBS(Residential Mortgage-Backed Securities=住宅ローン担保債券)(*注4)と呼ばれる債券は、何千件もの個人向け住宅ローンのプールから生じるキャッシュフローに対する請求権。これを「1次証券化商品」とする。
¬ RMBSをリスクとリターンによって切り分けた「トランシェ」毎に販売する。第1のトランシェは、金利は最も高いがデフォルトリスクが最も高い。最上位のトランシェは、金利は低いがデフォルトリスクが最も低いので、元はサブプライムローンでも「トリプルA」がついて、売りやすくなるのがカギ。
CDO(Collateralized Debt Obligation=債券担保証券)
RMBSの「トリプルB」トランシェをSPC(Special Purpose Company)と呼ばれる特別目的会社に移し、それを裏付けとして発行した債券を投資家に売却するスキームである。リスクによってシニア債(最優先に返済「トリプルA」)、メザニン債(シニア債に劣後「トリプルB」)として売られる。これが「2次証券化商品」だ。
CDS(Credit Default Swap)
信用リスクの売買をいうが、サブプライム住宅ローン債券がデフォルトになった場合の保険の一種と考えると分かりやすい。その対価として保証料(プレミアム)を毎年支払う。本書で、市場の破綻に賭けたアイズマンたちがCDOに対するCDSを買うことで、実質的に空売り(ショート)を行う(*注5)。
◆何が問題か
投資銀行は、売り難い「トリプルB」のRMBSを集めてCDOを作る。CDOは高い格付け(トリプルA)のトランシュを作り出すことができる。これを、高格付け債を求める機関投資家に売却する。「クズのトリプルB(*注6)を金ピカトリプルAに変える魔術」というわけだ。
➡案件を組成・販売する側は誰も責任を取らない仕組みであり、モラルハザードが生じやすい。最終投資家は「カモ」というわけだ。
➡証券化商品は、最終投資家から原債権が見えず、損失の所在が不明確。特に「2次証券化商品」にその傾向が強い。また、購入した商品は市場性がなく、価格も投資銀行が算出した価格を信用するしかない、問題が顕在化しにくい構造だ。
その後、CDO契約を裏付けに発行される「合成CDO」(*注7)が作られた。これによって元になる住宅ローンがなくても、いくらでもCDOを合成して作り出すことができるようになった。これを「3次証券化商品」と呼ぶ。
➡この結果、金融システムの被害が、サブプライム住宅ローンだけの被害より遥かに大きく複雑なものになってしまった。
投資銀行はリスクを転嫁しつつ巨額の手数料収入を得る。この仕組みはうまくいきすぎて、商品が供給不足に陥ったため、商品そのものを人為的に作り出すようになった。家を買うための住宅ローンであるはずが、逆に商品組成のためにサブプライム住宅ローンを作り出すようになったのである。頭金なし、返済猶予、釣り金利(*注8)といった手法で、返済能力にかかわりなく借りやすくしてサブプライム住宅ローンを乱造した。
➡収益をあげるため低所得層を犠牲にしたモラルハザードの一例。
では、なぜ高格付けが得られるのか。格付け機関(*注9)の論理は、「住宅ローンのプールを構成する各々のローンは均一ではなく、住宅価格の上昇が止まっても、一斉に債務不履行に陥るわけではない」というものだ。関連性はないという解釈で、「CDOの80%をトリプルAに格付けする判定を正当化した」と著者は批判する。これは「たくさん集めればリスクを劇的に減らせる」という企業ローンの実績から得られた経験則であったが、住宅ローンについても当てはまるかどうかは実績がなかった。
➡格付機関は、根拠の弱い経験則を援用し、手数料を稼がせてくれる投資銀行が望む格付けを出し続けた。モラルハザードの一例。
◆リーマン・ショックの本質としてのモラルハザード
登場人物たちは、「トリプルBからトリプルAを創り出す」サブプライム住宅ローン債券市場の怪しさに、薄々気づきながら自分個人の利益のためだけに行動する。そこには倫理観の葛藤は見られず、むしろ投資銀行同士の金儲け競争は激化していった。不動産の上昇が止まった時に、システムは崩壊し、当事者たちは稼いだ金を持って退場する。金融機関は痛手を負うが、金融システム全体の維持を名目に最終的に政府が救済したのである。
投資銀行とトレーダーがどれだけ稼いだかを、本書の例で見ておこう。ゴールドマン・サックスは、合成CDO 200億ドルの取引で、CDSを組み込んで実質的なリスクを米大手保険会社AIGに取らせた上で、最大30億ドルの手数料収入を得たとされる。債券のトップトレーダーの年収は5千万ドル以上といわれている。
ただし、だました側の投資銀行は、自らも大きな損失を被り、商業銀行に救済されて傘下に入るか、銀行免許を取って当局に救済された(*注10)。なぜ巨額の損失を出したのか。本書の結論は「私利私欲に目をくらまされ、自分たちの生み出したリスクに気が付かなかった」というものだ。自業自得というわけだが、投資銀行自体は姿形を変えてしっかり生き残ったと見ることもできる。
結局、最終的な被害者は、納税者と主な借り手であった信用力の弱い下位中流層ということになる。本書では、米国政府が負担したサブプライム住宅ローン関連の損失総額を1兆ドルとしている。約100兆円を納税者が負担したことになる。また、600万人が家を失ったとされる。なお、この他に各国の銀行や機関投資家も大きな損失を出し(*注11)、世界規模の金融危機、経済不況につながっていく。
著者は、登場人物の言葉を借りて次のように断罪する。
●金融市場は、人が他人をだまして金を儲ける世界
●金融システムは、貧困層を食い物にしている
●サブプライム債券市場の人々は「ぼんくらと詐欺師の集団」
●大手投資銀行は、「好景気のときは、政府の規制を疎んじ、不景気のときは政府の救済を強く求める」「儲けたときは自分のもの、損したときは納税者のもの」
リーマン・ショックの後、同じ過ちを繰り返さないため金融規制が強化された(*注12)。しかし、トランプ大統領の誕生で、規制緩和への圧力が強まっている。また、金融業界は、住宅ローンの代わりに自動車ローンを使ったサブプライムローンの証券化商品の取引を増やしているといわれる。米金融界の強欲主義は何も変わっていないようだ。
◆リーマン・ショックを生み出した経済成長至上主義
米国経済は約7割を個人消費に依存している。しかし消費需要はすぐに飽和する。そこで広告・宣伝によって「需要そのものを造出する構造」が作られた。この構造は、消費者の借金によって支えられている。すなわち、「豊かな社会」の平均的米国人は、意識せずに借金生活をしている。日常の買い物(米国人の国民的娯楽はショッピングである)、生活関連費はすべてクレジットカードで決済する。カード会社から毎月請求が来ると、ミニマム金額(2〜4%程度)の小切手を送付し、前月の残高と合わせて残りはクレジット(実質金利20%前後の借金)にする。収入が高くても支出が大きいので基本は同じである。要は自転車操業で、何かあると破綻するので皆必死で働く。
家は住宅ローンで買い、住宅価格が上がると担保余力分を住宅ローンで借り増しして追加の消費に回す。テレビ番組に出てくるような良い家に住んで、高価なドレスをまとい、うまいものを食べて、新しい妻(夫)を見つけて再婚する生活が、本当の人生(自己実現)だという強迫観念にかられて借金を重ねる。こうした生活構造と快楽主義が、リーマン・ショックを生み出した土壌だ。投資銀行のエリートたちの強欲とモラルハザードは、この構造が下から上までくまなく浸透していることの現れだ。
これは米国だけの話ではなく、程度の差こそあれ、欧州でも日本でも同様の「造出された」消費構造を持っている。そして、どこの国の政府も、国民が求めるいっそうの生活向上には経済成長(=いっそうの需要増出)が必要不可欠と信じており、高い成長率は与野党を問わず重要な選挙公約だ。しかし、「豊かな社会」が行き着いた先は、借金に支えられた需要造出システムなのであり、それは金融を通じてグローバルにつながっているのだ。経済成長を生み出す基盤となった倫理観が崩壊しつつあるにもかかわらず、現システム維持のために一層の「経済成長」が必要となっていると考えると、持続性のあるシステムとは到底思えなくなってくるのである。
<参考図書>
『世紀の空売り―世界経済の破綻に賭けた男たち』マイケル・ルイス著 東江一紀訳 文春文庫、2013年(原本『The Big Short』は10年に米国で出版)
(*注1)マイケル・ルイス(1960〜):米国のノンフィクション作家。『ライアーズ・ポーカー』(1989年)でデビューし、『マネー・ボール』(2003年)はベストセラーとなり映画化された。
(*注2)第88回アカデミー賞の作品賞を始めとする5部門にノミネートされ、脚色賞を獲得している。なお『ラ・ラ・ランド』主演のイケメン男優ライアン・ゴスリングが、投資銀行社員役で好演。
(*注3)住宅価格から既存の住宅ローン残額を差し引いた金額を上限として貸し付けるローンを指す。家の担保余力を現金化でき、当初は低所得者や信用力の低い人がカードローンより安い金利で借金できる「社会的に正しい」商品だと考えられた。なぜなら、米国では生活費はクレジットカードのクレジット(借金)で自転車操業するのが一般的。その場合の金利(20%前後)と比べれば、サブプライム住宅ローンは、元本返済はあるが金利は低いので(当初2年間固定6%→以降変動12%)、借り換えが有利と考えられたのだ。
(*注4)1980年代にモーゲージに裏付けされた債券(MBS)が開発された。当初の目的は、オフバランスによる住宅ローン市場の活性化、リスク分散した債券による機関投資家に対する投資機会の提供、金利の低下が可能で住宅ローン利用者に恩恵、などによって市場の効率性を高めることにあった。
(*注5)スワップ取引とは、同じ価値を持つキャッシュフローを交換する取引をいう。これを信用リスクに応用したものがCDSであり、企業の信用リスクをヘッジするための一種の保険として利用される。ここでは、それをさらに合成CDOに応用したCDSが登場する。
(*注6)「トリプルB」はマーケットでは投資適格とされ「クズ」という表現は正しくないが、本書では粗製乱造したサブプライム住宅ローン債券の「まやかし格付け」の「トリプルB」という意味で「クズ」と呼んでおりそのまま使った。
(*注7)合成CDO(Synthetic Collateralized Debt Obligation)は、複数のCDOを参照する信用リスク売買であり、CDSを組み合わせて、売り手としてプレミアムを受取ることでより高いクーポンを実現する。本書でアイズマンたちは、空売りのためにCDSを投資銀行から買ったが、その背後には合成CDOが存在した。CDSの売り手が合成CDOのリスクテイカーになっていたということだ。米大手保険会社のAIGがCDSの主な売り手であったが、市場破綻後、AIGは巨額の損失を抱え、最終的に政府に救済された。
(*注8)返済猶予:最初の数年間を返済猶予することで借りやすくする一方、以降の返済負担が大きくなる。釣り金利:当初数年間は低い固定金利で返済を楽に見せ、その後は市場の変動金利+5〜6%の高金利を適用する。固定金利期間が終われば、実質上返済不能になる。
(*注9)2大格付け会社といわれるのは、米国のスタンダード&プアーズ(S&P)とムーディーズ(Moody`s)である。リーマン・ショックで両社がトリプルAと格付けしたCDOがデフォルトとなったため業界規制が強化された。
(*注10)大手投資銀行は、商業銀行に救済され傘下に入るか(メリル・リンチがBOAの傘下に、モルガン・スタンレーが三菱UFJの持分法適用会社になど)、銀行免許を取って救済された(ゴールドマン・サックスなど)。
(*注11)日本の金融機関は、相対的に被害金額は小さかったが、本書では、市場が破綻する直前に手を出したみずほ証券が「最後のカモ」として紹介されているほか、サブプライム住宅ローン債券の大口の買い手として農林中金(この影響で巨額の含み損を出して大型増資)が登場する。
(*注12)2010年、米の金融規制改革法(ドット・フランク法)にボルカールールと呼ばれる銀行規制が盛り込まれた。過剰なリスクテイクを制限した。