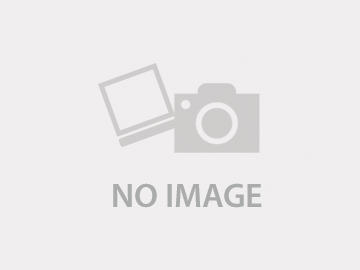調べる必要もないと思ったけど
当然つながってますね。
ちなみに、小ネタですが、週刊新潮もつながっていて、
吉松育美さんをディスった記事を書かせたみたいで。
その後、なぜかスノーデンの話についての本を週刊新潮から出版してたんですね。
その話があったら、プラスマイナスの意味で、スノーデンに踏み込んだのかなと思ったりしてたけど、
本の中身までは私は読んでないので、単に出しただけなのかなとも思えてくるし。
"芸能界のタブー"といわれるバーニングおよび周防郁雄社長に対して、歯に衣着せぬ批判を展開し続ける男・芸能ジャーナリストの本多圭。"親バーニング"一色の芸能マスコミの中にあって、これまでバーニングに訴えられること5回。
暴力団関係者から、威圧されたこともあるという......それでもなぜ、この男はペンで闘い続けるのか。
――本多さんは、これまでバーニングプロダクションの周防郁雄社長の批判記事を書いては、同プロに何度も名誉毀損で告訴されているそうですね。
本多(以下、本) 周防と暴力団の黒い交際や、メディアコントロールの実態、周防の素顔などを書いて、これまでに5回、名誉毀損での損害賠償を求められて、告訴されてるよ。そのうち4回は向こうが取り下げたり、和解になったりして、判決確定までは行っていない。残りの1件は、現在も控訴審で係争中。周防サイドは「和解をしておきながら、また似たようなことを書くというのは確信犯だ」と言ってるらしいが、何度書いても、周防がその姿勢を改めないからだよ。
――周防社長との因縁の始まりは?
本 「週刊ポスト」(小学館)の記者になりたての頃だから、今から35~36年前かな。当時、バーニングに所属していた歌手の南沙織(現・篠山紀信夫人)の男性スキャンダルが発覚したんだけど、その取材にいった「週刊新潮」の記者が周防と揉み合って、メガネを壊されたという情報を得たんだ。その真偽を確かめにバーニングの事務所に行って、「周防さん、いますか?」と声をかけたら、事務所を掃除していた男がいきなり、モップを振り回してきた。そのモップ男が周防だったのを記憶している。
――そのときの怒りが、周防社長に批判の矛先を向けるきっかけになったと?
本 そんな個人的な問題じゃないよ。ひとつは、その頃、ある大手芸能プロのオーナーから「せっかく日本音楽事業者協会が警視庁と連携して、芸能界と暴力団との関係を断ち切ろうと努力して、清浄化しつつあるのに、周防が逆行させている」という嘆きの言葉を聞いたんだ。
周防は、力を持つにつれ、暴力団との交際を深めていったんだよね。
――なぜ、周防社長は暴力団と付き合うんでしょうか?
本 好きなんじゃないの? 周防が芸能界に入った頃は、暴力団が芸能プロの経営や歌手の興業にかかわっていたりと、あちこちで接点があっただろうし、彼もそういう義理人情の世界が肌に合うんだろうね。ただ、子どもたちの憧れの対象で、社会の規範であるべき芸能界では、そうした付き合いは許されるべきではない。業界の総意として、脱暴力団を掲げていたのに、リーダー格たるバーニングがそれを守らなくてどうするんだと。
――なぜ、周防社長は"芸能界のドン"と呼ばれるまでになったと思いますか?
本 俺の見立てだけど、周防は、音楽出版ビジネスに着眼して、当時、TBSの音楽番組を牛耳っていた渡辺正文氏(故人)と組んで、日本レコード大賞などの賞レースもビジネス化していったんだよね。レコ大の審査にかかわるスポーツ紙の記者や音楽評論家などの芸能マスコミを高級クラブで接待して、彼らの誕生日にはパーティを開いてやり、プレゼントを贈る。
冠婚葬祭には、破格の祝儀や香典を出して、芸能マスコミと癒着関係を築いてきた。
レコ大を受賞したいと考えた芸能プロやレコード会社は周防を頼り、周防はその見返りに、その歌手の楽曲の原盤権や出版権などを握る。レコ大を受賞すれば、それらの権利がさらに大きな金を生み出すわけだ。ここで培った芸能マスコミとのパイプを生かして、スキャンダル情報などもコントロールできる。そうして巨大な資金力を培った周防は、さらに、いい人材を抱えていながら、資金力がない芸能プロに援助をして、売り出しをプロモート。系列の音楽出版社に著作権を持たせたり、興業会社に営業権を持たせたりと、金のなる木を作り上げていったんだ。
金もあり、マスコミも抑えて、ビジネスモデルも確立している。こうなると完全に"ドン"だよ。
――同じ記者として、バーニングに従属するマスコミをどう見ていましたか?
本 許せなかったよ。その後、「週刊ポスト」の記者を辞め、フリーになり、東京スポーツで仕事をするようになった。当時の東スポの局長から「うちの文化部は、芸能プロとの癒着が激しい。君、好きにやってくれないか」という打診があり、"俺は鉄砲玉か"という思いで、文化部の記者から疎まれながら、芸能の取材を始めたんだ。
芸能マスコミは、周防の黒い交際や所属タレントのスキャンダルを知っていながら黙認している。だったら、俺ひとりでもやってやろうと、バーニング系列のタレントのスキャンダルを東スポだけではなく、権力を怖れない「アサヒ芸能」(徳間書店)や「創」(創出版)、「話のチャンネル」(日本文芸社)といった媒体で次々に暴いていった。